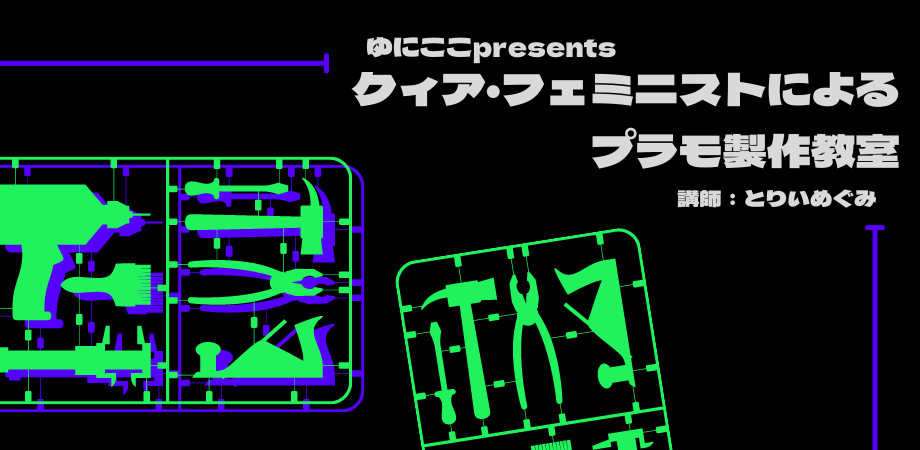ゆにここプライド特集、第二弾はラテンアメリカ映画を専門とする新谷和輝さんにご寄稿いただきました。中年女性カップルが過ごす静かな最期を描く映画『Vendrá la muerte y tendrá tus ojos(死が訪れ、君の目をさらっていく)』の希望をめぐる、評論エッセイです。
書いた人:新谷和輝
映画研究者、字幕翻訳者。チリやキューバの映画を学んでいる。
病を抱えたときにひとりでいるのは心細い。私は幼い頃に小児喘息を患っていて、ときどき発作をおこして入院することがあった。吸入をして喘鳴(ぜんめい)がいくぶんおさまったあと、病室の静かなベッドに横になるとき、隣にはつねに誰かにいてもらいたかった。今でも体調が悪いときに家でひとりきりになるとそのことを思い出す。だから、ウイルスがひろがっているこの社会で、隔離されて不安な日々を過ごしている人や、大切な人と触れあえずに亡くなってしまう人のニュースを聞くと、複雑な気持ちになる。毎日テレビをつければその日の統計上の死者数が目に入ってくる。誰かの死を看取ることについて、看取られることについて、ぐるぐると考えてしまう。
チリの映画監督ホセ・ルイス・トレス・レイバの最新作、『Vendrá la muerte y tendrá tus ojos(死が訪れ、君の目をさらっていく)』の話をしたい。不治の病を抱えたマリア(Julieta Figueroa)と、彼女の最期の時を共に過ごすアナ(Amparo Noguera)という、中年の女性カップルを描いたフィクション映画だ。現在、映画配信プラットフォームのMUBIで配信されている。日本語字幕はないのだが英語字幕がある。また、セリフも少ない。MUBIは無料お試し期間もあるので、もし見てもらえたら嬉しい。
この映画を見てまずいいなと思ったのは、年齢を重ねた女性カップルのたたずまいが、ありきたりな仕方ではなくて、おそらく長い時間をかけたであろう製作陣のやり取りによって、具体的な親密さとして画面に表れていることだった。二人が互いの頬をさすったり、見つめあったりする、そうした所作のひとつひとつに要約できない感情がこもっていて、ここにある時間はこの映画にしか現れない時間だと思った。マリアは治療をやめて、アナと一緒に過ごすために森のなかのコテージへ行くが、彼女たちに注がれる木漏れ日や、涼しげな風の音や感触まで、映画は彼女たちを取り巻くものをできるだけ掬おうとしている。
死が過剰にドラマチックに描かれていないこともよかった。映画に描かれるトランスジェンダーやレズビアンといった性的マイノリティとされる人々は、少なからず過酷な逆境に立たされることがある。そういった映画の結末には死が待っていることもよくあるが、その死にいったいどんな役割が期待されているのかを考えないといけないと思う。死がある人々の存在価値を測るために置かれていないか、死が物語を盛り上げるためのわかりやすい記号になっていないだろうか(これはいわゆる「余命映画」についても言える)。
この映画もマリアが死にゆくことは映画の冒頭から決まっているが、その死は私たち誰しもにいつか訪れるものとして透明に、それゆえ予想がつかない得体の知れないものとして、まずある。マリアが寝床の上で身体をよじらせ苦しむ様子をカメラはじっとみつめるが、そこには感傷的な音楽などつかず、観客はアナとともに見守るしかない。ここでは死に安易な意味を見出すことは避けられている。アナとマリアがどのような人生をおくってきたのか、その過去もこの映画では直接的に描かれない。しかし、彼女たちの沈黙や視線のやり取りから、そこに至るまでの茫漠とした時間を想像できる。そのはてしない時間を照射することからでしか、彼女たちの存在を考えることはできない。
ケアの観点から見ると、マリアだけでなくアナの苦しみもこの映画は描いている。アナの職業が看護師であることは偶然ではない。ケアをする側も人間であって、ひたすら奉仕できるわけではない。彼女も死の領域に足を踏み入れている。ふたりでいることはいいことばかりではない。そこにはうすっぺらな感動なんて吹き飛ばしてしまう、生々しい現実がある。
『死が訪れ、君の目をさらっていく』というこの映画のタイトルは、イタリアの詩人チェーザレ・パヴェーゼの同名の詩からとられている。この詩には死と視覚について触れられている箇所が多い。タイトルがまずそうで、ほかにも「君の目は無力な言葉だ」や「すべてにおいて死はまなざしをもっている」という表現がある(これらの日本語訳はスペイン語訳を参考にした拙訳である)。死という深淵を前にしたとき、私たちの視覚は力を失ってしまうということなのだろうか。この映画にも陽光をのみこんでしまうような深い暗闇が映る。しかし、それだけではない。この映画のなかでアナとマリアは、抱え込んだ重荷のためにすれ違うこともある。死がほんとうに目の前にせまっているとき、誰かと一緒にいることは苦しいのだろう。それでも、彼女たちは残された時間を見つめ返し、ふたりで生きようとしている。映画の冒頭でマリアがアナに目を瞑って車を運転してみてと頼むときから、先の見えない道をふたりで進むことがはじまる。彼女たちは死の視線にさらされながら、お互いを見つめ、一緒にいる方法を探っていく。だから、ここには死とともにある生のまなざしがあると思う。パヴェーゼは同じ詩のなかでこうも書いている。「ああ 愛しい希望よ あの日私たちはまた知ったのだ 君は生であり そして無であると」。死ぬことと生きることそのものに意味はないが、だからこそその無意味をわかちあえる誰かを求めるのかもしれない。
映画の途中に挟まれる、マリアの叔父のエピソードが印象深い。彼は死に際に、生涯で一度だけ愛し合った男性との思い出を自分に告白したのだと、マリアはアナに語る。その後、映画は湖畔で出会ったふたりの男性が愛し合う様子を映す。結婚して子どももいた叔父が最期に打ち明けたこの思い出は、彼にとって死を共に迎えるための大切な記憶となった。でも、叔父はこのことをあらかじめ決めていたわけではないと思う。隣にいたマリアにたまたま話す気になって、そのときになってはじめて自分にとってのその記憶の価値に気づいたのではないだろうか。
死は不意に訪れるし、人の死に方はさまざまだ。そのとき隣にいてくれるのは、家族か友人か信頼できるパートナーか、それかぜんぜん知らない人かもしれない。たとえひとりで死んでいくとしても、その人の身体に残っている記憶が拠り所となることもあるだろう。私たちはいつどこでだれと出会うかわからないし、同じように死に別れることもコントロールできない。そうしたままならない世界において、この映画でアナとマリアが最後までふたりでいることをあきらめなかったのはひとつの希望として映った。アナが映画の最後で見聞きする光景は、その希望の変奏だ。
この映画のほかにも、MUBIでは現在クィア映画が特集されている。一例として、チリでピノチェト独裁政権下からパフォーマンスを続けてきたクィア・アーティスト、ペドロ・レメベルの生涯を追ったドキュメンタリー映画『Lemebel』は見ごたえがあった。あらゆる規範にユーモラスに立ち向かったアーティスト/アクティヴィストの姿がよみがえる。多くの人に見てほしい作品だ。
この文章についてのご意見・ご感想は、以下のメールアドレスにお送りください。 unicoco@xemono.life