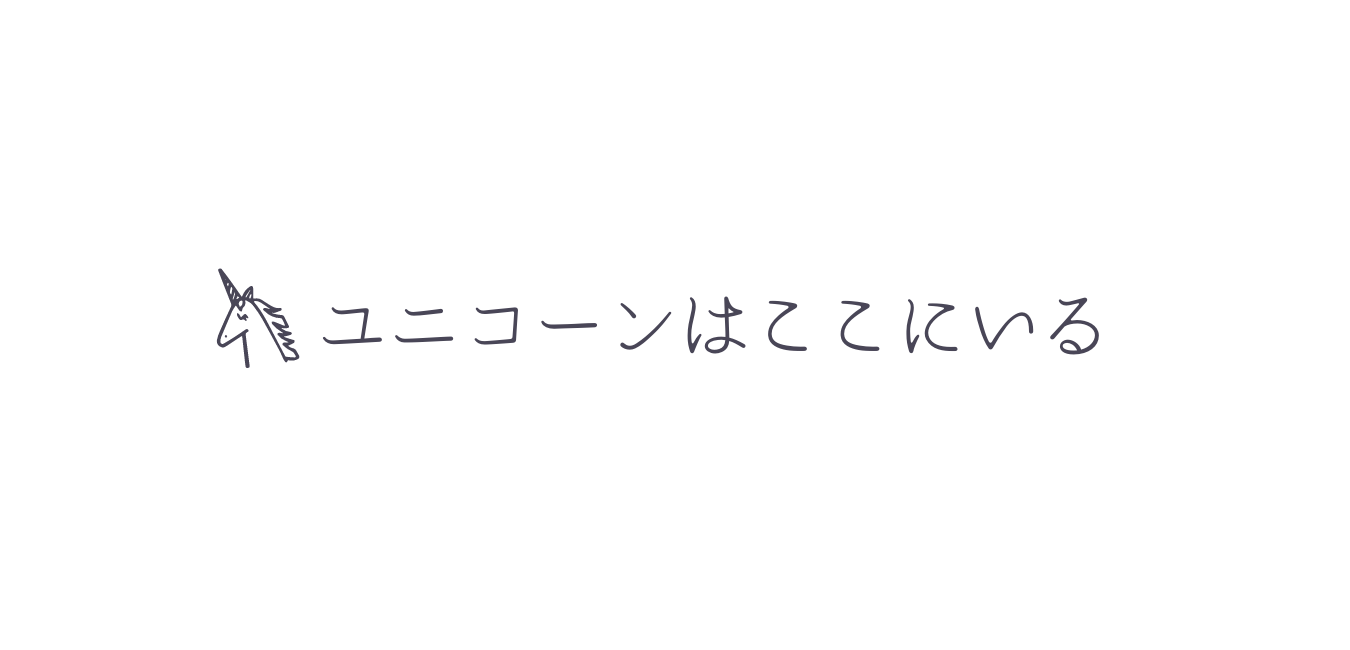わたしには憧れの家がある。
もうこの世界には存在しない家だ。
その家は、友人の叔母さんにあたるひとが所有していたのだけど普段は違う場所で生活をしているらしく、いつ訪ねても持ち主に会う機会がないままだった。
わたしは古着を売る仕事をしてきたので、持ち主に会わずに誰かの持ち物を見る機会がこれまでも多くあった。ポケットのなかに砂糖が入っているジャケットや、レシートの入ったジーンズには会ったこともない人間の生活のあとが必ずついてくる。それらに触れるたび「ポケットの中に、グミ入れたでしょ」とか見知らぬだれかに対して思ってきた。
その家も、会ったことのない人間の生活が空間中を満たしていた。
一つひとつを、誰かが選び、整えたあとがあった。
まず屋根が印象的だった。
お誕生日のときに被る帽子みたいな屋根がちょこん、と筒状の建物に乗っていて、都会的でスタイリッシュな雰囲気のマンションが並ぶそのエリアで、一軒だけいつもお誕生日会の呑気さや楽しさみたいなものをまとっているようだった。
家の中には光がよく差し込む玄関があった。光の道筋を目で追うと、窓が二つあり、まっしろいフリルのカーテンが付いている。

廊下を歩くと、天井の高いリビングに辿り着く。部屋の右側の壁ほとんど全てを覆う窓と、グランドピアノとチェロ、立派なダイニングテーブルと、大きな鏡。階段に使用されている木は、登ったら森へ続くんじゃないかとおもうほどに生き生きとしていた。

年に数回、わたしは友人たちと一緒にこの家に数週間滞在し、夏休みや冬休みを過ごした。
東京からずっと離れた場所にあるこの家は、わたしたちの第二の家みたいな存在だった。

この家にくると決まって、近所にあったリサイクルショップで友人たちと激安なお洋服を買い込みファッションショーをして遊んだ。
激安だけれど、いまのわたしが一番にこれを楽しんで着れるはずだと、確信できるお洋服たちだ。友人たちが選んだ服をみると、より強くそう思えた。
そんなに貝殻のついたお洋服、持ち帰ってくれるひとなんてきっとそんなにいないだろう。
我々が持ち込むものは、たぶんここに置いてあるものとは桁が一つか二つ、違うはずなのだけど、不思議とどんなものを置いてもなじんだ。家にも懐の深さがあるのかもしれない。
「ただいま!」とずうずうしく、この家に上がりこみ、くつろぐわたしたちと、古着たち。
この家で、どんなひとが、どんなことを思い、毎日を送ったんだろう。
この家に流れる時間を確かに感じながらそんなことを思った。
ある朝、七時ぐらいだっただろうか。
連泊し、すっかり居心地よくなっていた朝だった。
二階のベットルームで寝ていると、下の階から香ばしい香りがしてきて、聞き覚えのないハキハキした声が聞こえた。
下へ降りると、着心地の良さそうなトップスにつつまれた坊主のひとがいた。
となりに、友人がいて「このひとが、この家の主で、わたしの叔母だよ。はっちゃんていうの」と紹介される。
香ばしいにおいは、この人が作るパンの香りだった。
クロワッサンとロールパンを作る手際が完璧で、見とれてしまい自己紹介がうまく頭に入ってこない。

「さあ!発酵させるか」とはっちゃんが言った。
階段下に置かれていた業務用の冷蔵庫みたいなものが、パンの発酵機であったことをわたしは初めて知る。

家が、あるべき人の手によって動き出すようすをみる。
パン生地を伸ばす棒は、キッチンの左から二段目の引き出しにあった。使ったことも、見たこともなかった棒。
セピア色の写真が、カラー写真になっていくようだった。
はっちゃんが家を隅々まで使っている様子をみて、嬉しい気持ちが湧いてくる。
めぐっていくものたちを、次の持ち主へつなぐ仕事をしていたわたしは、ものが持ち主の手になじんだ状態で存在できていることにたぶん人一倍弱い。
もしくは、誰かの手から離れていくものがあるとするならば、次の持ち主のところで、うんと大事にされますようにと願う。
そのために自分がいるのだと、仕事をしてきた。
だからはっちゃんが「この家を手放そうかと思ってる。管理も大変で。壊して、マンションにしようと言われているの」といったとき、横で聞いていた友人とどうか残してくれないか、こんな素敵なお家を壊すのはかなしい、とできうる限りの言葉を持って伝えた。
取り壊しの話はそれからも何度か話題に上った。
もういっそのこと、あの家にみんなで住む?と友人たちと話した日もあった。
自宅がある街から新幹線で数時間の場所にあったため、叶うことはなかったけれど、そのぐらいこの家を残したかった。
まったく知らなかった他人の家にこんなかたちで首を突っ込むなんて、存在がクィアすぎてちょっと笑う。
去年の春、家の取り壊し日が決まったと友人から連絡があった。
あっという間の出来事で、連絡を受けてからすぐに家はなくなった。
友人がずっと欲しかった、大島弓子の背表紙がきれいな漫画は、ゴミとして捨てられてしまったらしい。
そういう事実が一年以上たった今でもぼんやりとわたしの心のなかに残っている。
ものが残る、ということ、それがめぐっていくということそれ自体が得難いことなのかもしれないとわたしはそのとき初めて知った。
・
はっちゃんがパンを焼いてくれた日のことを振り返る。
朝からこねたパン生地をオーブンに入れ、あと数十分で焼き上がるぞ〜というときに、はっちゃんは鞄からカップヌードルを取り出した。
はっちゃんが作っているのは、天然酵母のパンだ。早朝から作ってる。
まさか、今食べるわけじゃないだろう、とおもったが、迷いなくカップヌードルにお湯を注ぎ始めた。
はっちゃんは「はやいからさ、好きなんだよねカップヌードル」といいながら楽しそうに麺をすすっていた。
わたしはそれを思い出すたびに、あんな素敵な家にあっけなくさようならをいえるのは、はっちゃんだからなんだと笑ってしまうのだった。
・著者プロフィール
杉田ぱん
フェミニストでクィアなギャル
Twitter:@p___sp