「フェミニズムとかもう古いよね」と高校生のわたしは言った。
わたしは女子校に通っていて、女の子だからと何かを制限された経験がなかった。
両親は共働き共家事で別姓で、世間では男女平等がとうに達成されているものと思っていた。
もう世の中男とか女とか関係なくて、女性差別とか言い出す方が性別に固執しているのだと思っていた。
家庭科の授業で、性差別を受けた経験を問われると、反発を覚えた。
それに、自分が「女性」としてカテゴライズされるのが何だか嫌だった。
小説などに出てくる「女性」は、思っていることをはっきり口に出さなくて、謎めいていて気まぐれで、ずるくて軽薄で中身が空っぽで、たいてい色恋が主な存在意義。
わたしとは関係のない生きもの。
なりたくもないもの。
といって男性になりたいわけでもなく、自分のことは性別のない透明な存在だと思っていた。
自分のことを性別のない存在だと思っていれば、何の問題もなくそういられるのだと信じていたのだ。
大学受験のとき、同級生が「あんまり偏差値の高すぎる大学に行ってしまうと嫁の貰い手がいなくなるって親に言われた」と言うので、「化石……!」と笑ってしまったことがある。
共学の大学に入ったら、化石の森だった。
同級生と昼食の席を囲んでいるだけで喧嘩になる日々だった。
なぜなら、わたしがお弁当を食べていると、かれらは「それ、自分で作ったの? お母さんに作ってもらったの?」と聞いてくるからだ。
律儀に毎回「父親が作ってくれたんだよ」と答えると、「お父さんに作らせてるの!? 自分で作りなよ!」と言ってくる。
それでわたしは、「『お母さんに作ってもらった』って答えてたらそんなこと言ってた!? わたしが男だったらそもそもそんな質問してた!?」と問い返す。
「料理できないの!? お嫁に行けないじゃん」と言われたこともあったし、将来大学院に進もうか就職しようか悩んでいたら「お嫁さんになればいいじゃん」と言われたこともあった。
「男とか女とかもう関係ない」と自分で思っていても、周囲が勝手に「女性」の役割やイメージを押し付けてくるのだと知った。
男性が八割のその大学で、女性が対等な人間として見られることはなかった。
「人間」は男性で事足りていて、女性はオプションとして存在しているという雰囲気がそこにはあった。
男性とは全く異なる生きものであるはずの、男性にとって何らかの利益をもたらすためにそこにいる存在。
見て楽しむためとか、承認欲求を満たすためとか、恋愛の相手になるためとか。
恋愛対象として見られたくないといくら言っても通じることはなかった。
交際を断っても、駆け引きとしか取られなかった。
そんなつもりはないのに、気を持たせている、男性を弄んでいると非難された。
それも仕方のないことではあるのかもしれないと思った。
だって、女性は気まぐれでミステリアスで、思ってもいないことを言い、思わせぶりな態度を取るものと相場が決まっている。
どんな小説にもそう書いてある。
わたしはそういう女性じゃないけど、それは伝わらないんだろうな。
そんなある時、高校時代に読んだことのある小説を再読して驚いた。
「気まぐれでミステリアスで、男に気を持たせるファム・ファタル」として描かれている(と、以前読んだときは受け取っていた)はずの女性の描写が、「はじめから男性のアプローチに対してノーと言っている」ようにしか見えなかったからだ。
アプローチされて、相手の気分を害さないようにノーを言いたかったら、わたしだって同じ行動をするだろう。
ミステリアスだったはずのその女性の内面が、手に取るようにわかった。
その時気付いた。
「曖昧な態度を取って男性を翻弄する」女性像というのは、現実の女性を反映したものではないのではないか?
男性側が相手の拒絶を拒絶と思いたくないあまりに、「拒絶めいた態度を取って気を持たせようとしている」と曲解に曲解を重ね、最後にどうしても「これは拒絶だ」と気付かざるを得なくなったときには「相手が急に態度を変えた」ことにしているだけなのではないのか?
わたしが「自分はそうじゃないから一緒にされたくない」と思っていた女性たちというのは、男性にとって都合よく作られた虚像に過ぎない。
その虚像に、わたしもいま、どんなに抗っても、自分は違うとどんなに言っても、嵌め込まれているのだ。
男とか女とか関係ない、というのは、本質的にはそうなのだけれど、現実においては「男性」や「女性」というラベルに意味があると思っている人があまりに多いがゆえにそのラベルに意味が生まれてしまっているということ、
男とか女とか関係ないと思っていると、自分に付与されてしまったそのラベルをいつの間にかほんとうに自分のものだと思い込まされてしまいそうになるということが、その時わかった。
自分が「女性」と見なされていること、「女性」がどういう存在だと見なされているかということに向き合って、その都度「自分」を取り返さなくてはならないのだ。
「世間一般の女性のイメージ」に当てはめられたくないからフェミニズムを拒絶するのではなくて、「世間一般の女性のイメージ」から解放されるためにフェミニズムが必要なのだと理解したのはその時だった。
それ以来わたしはフェミニストとして生きているし、いまでも自分のことは性別のない存在だと思っている。
画一的な「女性」の虚像(を、信じている人たち)に苦しめられてきたから、それに当てはまらない自分のまま生きて、その姿を人に見せること自体がフェミニズムの実践だと思っている。
このたび、フェミニストの友人たちと一緒にウェブメディアを立ち上げることにしたとき、一番に思ったのは、いろんな人がいろんなふうに生きているのを見てほしい、ということだった。
女性に当てはまる人も当てはまらない人も、クィアに当てはまる人も当てはまらない人も、鋳型からはみ出して好きに生きているところを見せてあげてほしい。
それだけで誰かの助けになるはずだから。
・著者プロフィール
川野芽生
ゆにここ編集長。短歌、小説、エッセイ、評論、論文などを書いています。
twitter: @megumikawano_

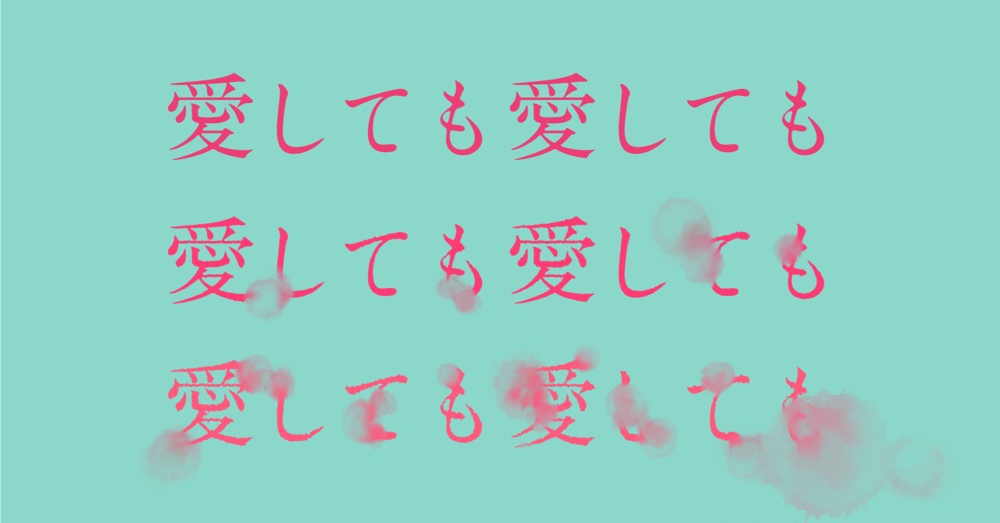
> 自分が「女性」と見なされていること、「女性」がどういう存在だと見なされているかということに向き合って、その都度「自分」を取り返さなくてはならないのだ。
これこれ。これを上手くやる方法を身に付けている人はいいですよね。それも自分が嫌な気分にならないやり方を。