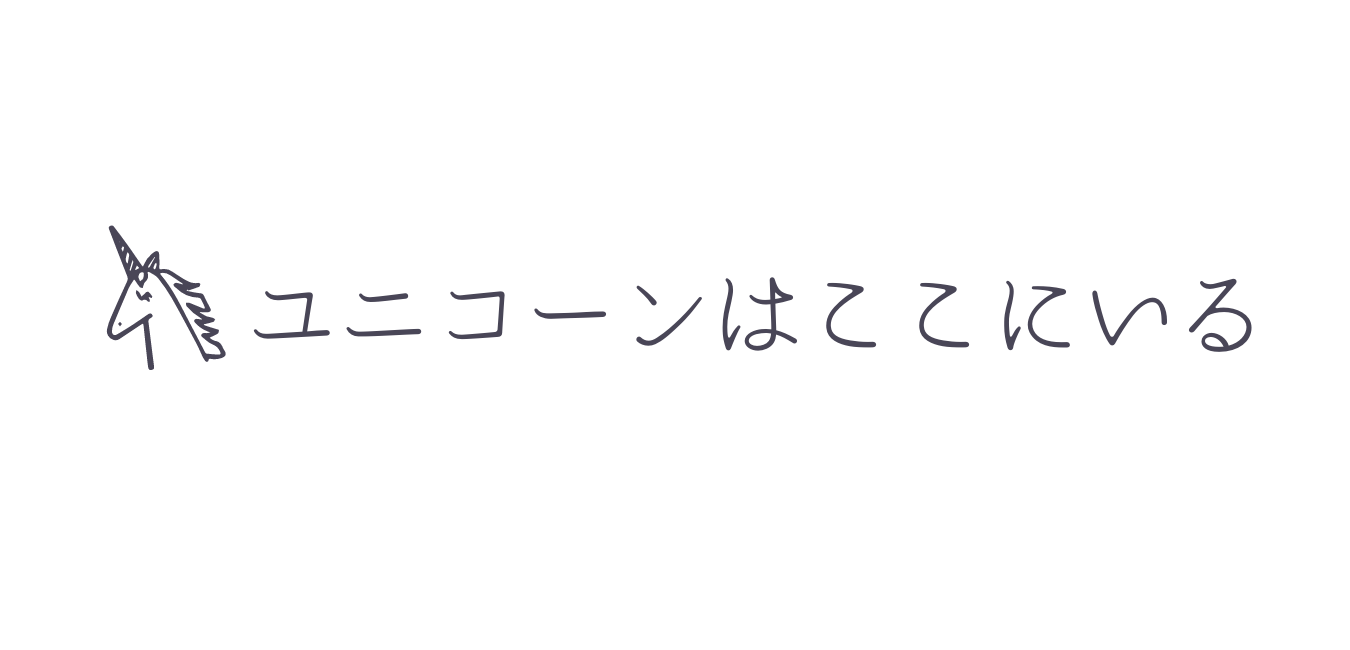わたしは、人の顔を覚えるのが苦手だ。
たとえば喫茶店で、友だちと向かい合ってお茶をしていたとする。アイスティーが運ばれてきて、シロップを注ぎ、ゆらゆらとアイスティーとシロップがまじりあうのをみつめると、もう目の前の人間の瞳がどんなふうだったのか、頭のなかで思い浮かべることができない。
その人と、どれだけ長い時間を過ごしたって、たとえそれが一緒に暮らしている人間であったとしても、覚えられる自信がない。
けれど、その人がその日、どんなものに包まれていたのか、たとえば、履いていた靴がスウェード素材のスニーカーだったこと、オルタナティブバンドのTシャツをよく着ていること、前髪が先週会ったときよりも短くなっていること、アイシャドーと口紅の色が同系色でまとまっていること、イヤリングの色とネイルカラーが補色どうしでひびきあっていること、眼鏡はブルーライトをカットするためにかけていること、家のなかでよく左右のちがう靴下を履いていること、目の前の人が、その日、選んだものについては、鮮明に覚えておくことができる。覚えていていたいとおもう。
「うまれもったもの」について、この社会では、なんだかとっても意味をもってしまう。瞳の色や、かたち、肌の色味や、身長、胸、おしり、脚、指、毛。
「今日は、脚をいつもより伸ばしたいな~」とおもっても、人間の脚は伸びない。わたしたちが自由に選べないものについて、比べあい、おまけに優劣までつけてしまったから、人間の社会は大変、愚かだ。
それは人間がつくった、あほらしい価値感だとはっきりと、だれかに言ってほしかった。
だから、自分で言うことにする。
所詮、人間がつくった価値なのだ。人間が書き換えることだって、できる。
そういうわけで、みなさまお集りいただきまして。わたしと、あなたと、いまはまだ出会っていないあなたと、一緒にお話ししてみたい。
わたしたち、一人ひとりを包むものについて。
・著者プロフィール
杉田ぱん
フェミニストでクィアなギャル
Twitter:@p___sp