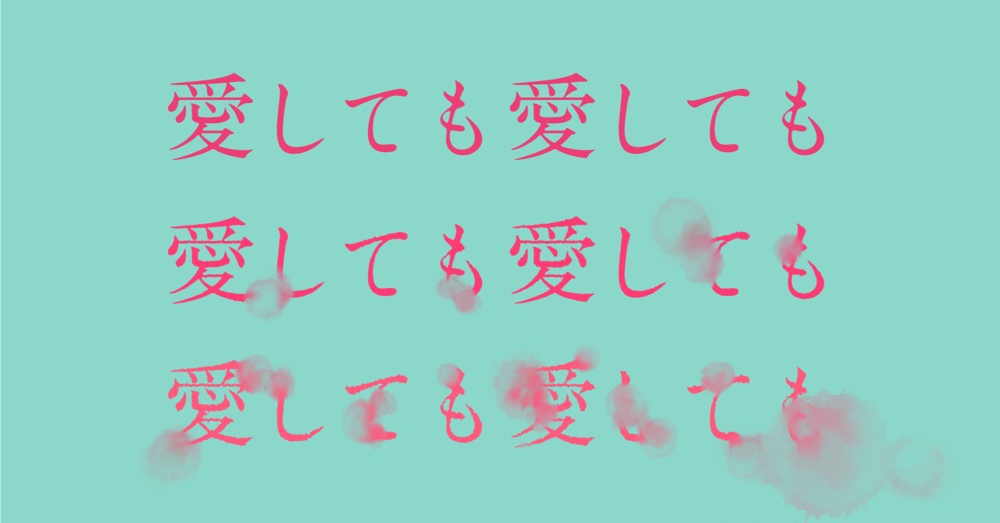読売新聞と全国の公立美術館で作る美術館連絡協議会が企画した「美術館女子」なるプロモーションが、話題になっている。
AKB48チーム8のメンバー(読売新聞で「月間チーム8」を連載中、という縁のようだ)が、各地の美術館で写真撮影を行い「写真を通じてアートの力を発信していく」企画とのことだ。

画像はhttps://www.yomiuri.co.jp/s/ims/bijyutukanjyoshi01/をキャプチャ。
「美術館女子」ーー「○○女子」と呼ばれることに疲れた女性たちにとって、この企画は違和感だらけであったに違いない。
フェミニストとして言いたいこともたくさんあるのだが、この記事ではそれに加えて「美術館、博物館とはどのような場所か」「美術館、博物館が抱えている問題がこの企画とどのように関係するのか」「広告マーケティングとして成功しているのか」など、いくつかの異なる視点からこの企画について考えてみたいと思う。
というのも、わたしは
・大学時代は美学専攻の学生として美術や博物館学について学び
・新卒で私設の文化施設に就職して裏方として働き
・現在は広告代理店で働いている
という、言うなればこの企画の当事者たちと絶妙に近い位置にいる人間なのだ。
そして、言うまでもなく、わたしはフェミニストである。
ではまず、美術館や博物館、ひいては「文化施設」が長く抱えている課題について考えてみよう。
文化施設の危機とマーケティング
まず、法制上は美術館は博物館の一種である。
あまり知られていないが、「博物館法」という法律があり、この中にいわゆる狭義の博物館、美術館、動物園、水族館などのあり方や、学芸員の仕事について定義されている。
学芸員資格を取得しようとする学生は、全員がこの博物館法について勉強することになる。
驚くべきことに、博物館法の中にはこのような条文がある
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000285#105
第二十三条 公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。
えっ、と思う人も多いであろう。公立博物館は、本来入館料を取ってはならないのである。
いやいや、入館無料の博物館や美術館もなくはないけれど、基本的に1000円から高いときには3000円近くの入館料を払って、わたしたちは展示を見にいきますよ。あれって違法なんですか?
いえいえ、ちゃんとこの条文には以下のような但し書きがついていますよ。
但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
そう、わたしたちが美術館や博物館に展示を見に行くときに払っている入館料は、彼らが「やむを得ない事情」で徴収しているものなのだ。
つまり、公立博物館・美術館は、営利目的で運営されてはいけない。でも施設の維持や展示品の保存、研究、人件費には当然莫大なコストがかかる。それを、仕方なく入館料で補わざるを得ない、ということだ。
公立美術館は利益を出すことを目的にはできない。しかし、来館者が少なければ運営費をまかなうことができない。
これは博物館・美術館がこれまでずっと抱えてきたジレンマだった。
本来は市場経済の外側になければいけないはずの公共施設が、しかし市場の原理の中で生き残っていかなければいけないのである。
そして、コロナ禍によってそのジレンマは、現実的な大きな危機として襲い掛かってきたに違いない。
誰も来館できないとはいえ、施設や展示品を放置しておくわけにはいかない。
絵画をはじめとするアート作品は、とてもわがままだ。気温も湿度も照明も適切に管理されていなければ、あっという間にボロボロになってしまう。
展示室に飾ってあった作品は、長期休館が決まった時点である程度収蔵庫に戻す必要があっただろう。
しかし、突然再開館が決まったら、また展示品を展示室に配置して、それにまだ感染リスクがあるから感染対策の備品も買い足して、来場者数を制限するための方策を考えて……
むしろ通常の開館中よりも内部スタッフの苦労や労働は増えたかもしれない。
そして、いざ再開、となったとき、以前と同じように来館者がくるとは限らない。
まず混雑しそうな展示は時間帯や入場者数の制限をかけなければいけないだろうし、まだまだ人込みへの外出を避ける人たちも多いだろうから、ぐっと入館料収入は減るだろう。
さらには、「新しい生活様式」の定着により、「美術館や博物館へ出かける」という習慣をもつ人自体が減ってしまう可能性すらある。
なんとしてでも、美術館を守らねばならない、となったとき、マーケティングやプロモーションのための施策を行う、というのは、当然の結論だったはずだ。
だからこのタイミングで大々的に「地域の公立美術館」をPRする企画が出てきたことは、不思議でも何でもない。
ではなぜ、こんな妙なプロモーションが世に出ることになったのだろうか?
誰のための企画だったのか?
マーケティングやプロモーションを行うとき、もっとも重視される要素の一つが「誰に向けて」か、ということである。
そのサービスや製品の熱心なファンなのか、あるいはもっとも縁遠い人々か、あるいは同業他社のサービスや製品を利用している人か。
わたしがもし美術館のプロモーションを依頼されたら、おそらく「20代後半~40代くらいの男性」をターゲットに設定するだろう。
展示内容や各館の特徴、曜日によって来館者の性別や年齢はかなり偏るので一概には言えないが、美術館や博物館に足を運ぶ人で多いのは
・校外実習などの団体児童・生徒
・高校生・大学生
・定年退職後であろう高齢者
・親子連れ
で、それ以外でも女性が6割、男性が4割くらい、という印象である。
この感覚に近い結果のアンケート結果もある。
https://www.momat.go.jp/ge/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/19_pp.26-41.pdf
だとすれば、比較的美術館や博物館に縁遠い20代後半~40代くらいの男性をターゲットにすることで、新規来館者を増やすきっかけが作れるのではないか、というのは、自然な発想であろう。
もちろん既存の利用者が離れないようにするプロモーションも当然行われるべきであるが、今回の企画でAKB48を起用する、となると、やはりそれは「20代後半~40代男性」をターゲットにする、と考えるものではないだろうか。
しかし、今回の企画は「美術館女子」と題して、まるで「美術館は女性が大好きな『映え』スポットですよ」とアピールしているように見える。
しかし内容はといえば、アイドル写真集やグラビアのような文法で撮影された写真をメインコンテンツとする、非常に男性向けらしいものなのだ。
ここが、この企画のいびつさにつながっているのではないか、というのがわたしの考えだ。
美術館は誰のものか
ここで、美術館・博物館とはいったいどのような場所なのか、という根本的な問題について考えたい。
あくまでわたしの考えではあるが、美術館・博物館とは、「文化と教養の民主主義の砦」である。
どういうことか。
芸術作品は、今までの歴史の中でほとんど権力者に「独占」されることで価値をもってきた。
画家は王や王妃、富豪、高位の聖職者に雇われて肖像画を描き、貴重な工芸品や古代の彫刻などは城や屋敷の中にしまい込まれた。
権力や財力をもたない多くの人々が芸術作品に触れることができるようになったのは、まさに「ミュージアム」という理念の誕生によってである。
前述したとおり、本来博物館法は公立博物館が入館料をとることを禁じている。
つまり、町の図書館と同じように、あらゆる人が出入りし、芸術作品を鑑賞し、楽しんだり考えを深めたり、あるいはただぼんやりとそこにいるだけでもいい、そういう場所として設計されているはずなのだ。
実際、多くの美術館や博物館では、入館料が必要な展示室以外に、だれでも出入りできるスペースを備えている。
散歩したり、図書資料を読んだり、ぼんやりしたり、友人と待ち合わせをしたり、そういうふうに美術館や博物館を利用したことがある人もいるだろう。
美術館や博物館は、すべての人にとって居心地のいい、文字通りの公共施設であるべきなのだ。
ここで思い出されるのが、「美術館ナンパ」とか「ギャラリーストーカー」とか呼ばれる現象の存在である。
2017年に「GG」という雑誌に「美術館にいる若い女性をナンパする」ことを勧めるような内容の特集が掲載され、物議をかもした。
https://www.excite.co.jp/news/article/E1497250971296/
この特集は読むに堪えない偏見とミソジニーのオンパレードなのだが、この特集を別にしても、美術館や博物館で知らない男性に突然話しかけられたり、ナンパされたりしたことがある女性というのは、それなりにいるのではないだろうか(わたしはある)。
あるいは、数年前に大々的に「春画展」が行われ、女性の美術ファンも多く訪れた、と話題になったが、その会場に足を運んだ時も、「春画を鑑賞する女性をじろじろ見ている男性来館者」を見かけて、うう、とつらい気持ちになった。
実際体験したことがない人には想像しづらく、ともすれば「自意識過剰では?」と言われかねないことかもしれないが、美術館に足を運ぶ女性の中には、一部の男性からこのような視線にさらされ、ストレスを感じる人がいるのである。
たかがナンパと思うかもしれないが、人によってはナンパされたことがある場所にはもう近づきたくない、となってしまうこともある。
わたしは常々、「ココはナンパOKの場所です」とデカデカと看板を出してエリアを区切り、ナンパしたい人とされたい人はそこにだけ集まって楽しくやり、それ以外の人はそこにはいかない、というシステムにしてくれればみんな幸せになれるのになあ~と思っている。そして最近は実際にそういうシステムのバーやイベントが増えてもいる。
やっかいなのは、「ナンパOK」の看板が出ていないのに、ある人は「ナンパOK」だと思っていて、またある人はそうではないと思っている場合である。
それが美術館や博物館であればどうだろうか?
ナンパや声かけを恐れて美術館に行くのを躊躇する人がいるとすれば、それは美術館が「文化と教養の民主主義の砦」であり、「すべての人に開かれた公共空間」としての役割を失ってしまうことになる。
「美術館女子」の何がいけないのか
「美術館女子」企画に話を戻そう。
「美術館女子」は一見若い女性に「映え」をきっかけに美術館の魅力を訴求する企画に見えて、中身は男性をターゲットにしたプロモーションである、というねじれを抱えている。
それゆえに、このプロモーションはまるで
「若い女性は「映え」のために美術館に来ましょう。男性はその女性を目当てに美術館に来ましょう」
というメッセージをパブリックに発信しているように見えてしまうのだ。
ミソジニーというほかない。
そして、このプロモーションを行うことによって美術館を今まで積極的に利用してきた女性たちに、ミソジニー的であるという悪い印象をもたれ、さらには美術館の「すべての人に開かれた公共空間」という重要な側面を脅かすという、致命的にマイナスの効果を生み出してしまった。
では、なぜこんな企画が世に出たのだろうか?
広告代理店的な観点でいうと、「たぶん誰か偉い人がやりたいって言ったんだろうな……」である。
いったいその「偉い人」がどこに所属している誰なのか、一人なのか複数なのか、それはわからない。
だが、こういう一貫性のない企画が大々的に発表されるときには、たいていオジサン的発想の偉い人が理屈を無視してごり押ししてくるものなのだ。
どうやら読売新聞は「美術館女子」企画を今後も続けていきたいらしい。
本当に公立美術館と利用者のことを思うなら、来館者のこともマーケティングの基本も理解していない謎の「偉い人」のいうことは思い切って無視して、「誰にとっても居心地のいい美術館」「地域の人に芸術の面白さを伝える美術館」の姿を伝えられるように、企画の見直しを考えてはどうだろうか。
・著者プロフィール
吉田瑞季
オタクに夢を売る仕事をしているオタク
演劇・古典芸能・ヤクザ映画・詩歌